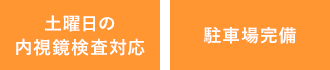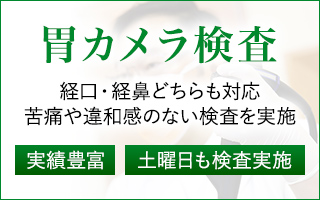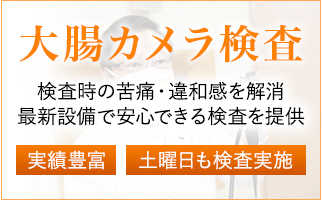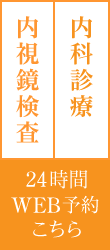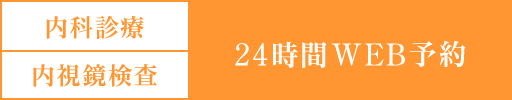胃の不快感や胸やけなどが長く続き、「慢性胃炎」と診断されると、不安に思われる方も多いかもしれません。そもそも慢性胃炎とは、長期間にわたって胃の粘膜に炎症が生じている状態を指します。ここでは、胃の中ではどのような変化が起こっているのか、治療や食事、そして生活習慣の面でどんなことに注意すればよいのかを、お伝えしていきます。
まず、胃の粘膜は、普段は胃酸や消化酵素から自らを守るために粘液を分泌しています。しかし、何らかの要因でその防御機能が弱くなると、粘膜が炎症を起こしやすい状態に陥ります。慢性胃炎の代表的な原因として挙げられるのが、ヘリコバクター・ピロリ菌(以下ピロリ菌)の感染です。ピロリ菌は胃の粘膜の中に生息し、粘膜を守る構造を傷つけたり、炎症物質を放出したりすることから、長期的に胃へのダメージを与えると考えられています。また、鎮痛薬の一種である非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)を常用することで、粘膜が刺激を受けやすくなり、慢性的な炎症につながることもあるのです。 さらに、アルコールの過度な摂取や喫煙、強いストレス、あるいは唐辛子など刺激の強い食事の摂りすぎも、慢性胃炎を悪化させる要因になるとされています。こうした要因が重なると、胃の粘膜が薄くなってしまい、胃酸の刺激を受けやすくなる「萎縮性胃炎」に至るケースもあります。この状態になると、みぞおち付近に鈍い痛みや不快感、胸やけ、吐き気、食欲の低下などの症状が現れやすくなりますが、症状がはっきりしない方も少なくありません。そのため、医師の診察や内視鏡検査による正確な診断が重要となります。
治療の基本は、まず原因を特定し、それを取り除くことです。もしピロリ菌感染が見つかった場合は、除菌療法(複数の抗生物質と胃酸分泌を抑える薬を組み合わせた治療)を行います。除菌が成功すると、粘膜の炎症が徐々に落ち着いていき、萎縮の進行を抑えられる可能性が高まります。また、除菌の対象とならないケースでも、胃酸の分泌を抑制するプロトンポンプ阻害薬(PPI)や、ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)、粘膜を保護する薬などが処方され、症状の緩和や胃粘膜の回復が期待できます。
次に、食事についても留意すべき点がいくつかあります。辛味の強い調味料や脂っこい料理、炭酸飲料や過度なアルコールは、胃を刺激する可能性が高いので控えることをおすすめします。コーヒーや紅茶、緑茶などに含まれるカフェインも胃酸の分泌を増やすことがあるため、摂取量には気を配ると良いでしょう。一方で、煮込み料理やおかゆ、豆腐、白身魚など、消化に優しい食材を中心に献立を組むと、胃への負担を抑えることができます。また、暴飲暴食や寝る直前の大量摂取は胃の働きを妨げるので、食事時間や食べる量も見直す必要があります。
生活習慣に目を向けると、まず挙げられるのが禁煙です。タバコの成分は血流を悪化させて粘膜の再生を阻害するため、胃炎の回復を遅らせるといわれています。さらに、ストレスの多い生活を送っていると、自律神経が乱れて胃酸の分泌量が増えたり、胃の蠕動(ぜんどう)運動が低下したりしやすくなり、症状が長引く可能性があります。そこで、適度な運動や十分な睡眠を心がけ、趣味やリラクゼーションを取り入れてストレスを軽減することも欠かせません。加えて、アルコールを頻繁に飲む習慣がある方は、なるべく摂取量を控えたり、ノンアルコール飲料を活用したりするなど、胃への負担を和らげる工夫をしてみてください。なお、慢性胃炎が進行して粘膜の萎縮が強まると、将来的に胃がんのリスクが高まる可能性も指摘されています。そのため、定期的に内視鏡検査を受け、医師から必要な指示をしっかりと受け取ることが大切です。処方された薬を自己判断で中断したり、自己流の対策のみで過ごしたりすると、症状が悪化するおそれがあるため注意しましょう。わからないことがあれば、医療機関で遠慮なく相談することが、より良い治療への近道になります。
このように、慢性胃炎は胃粘膜が長期的なダメージを受け続けている状態ですが、適切な治療や日頃の習慣改善によって症状を落ち着かせ、将来的なリスクを減らすことも可能です。生活面の工夫や医師の指導を取り入れながら、焦らずに身体と向き合い、胃のコンディションを整えていきましょう。